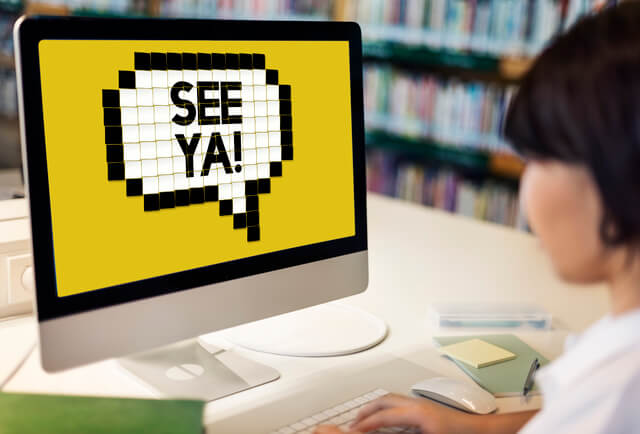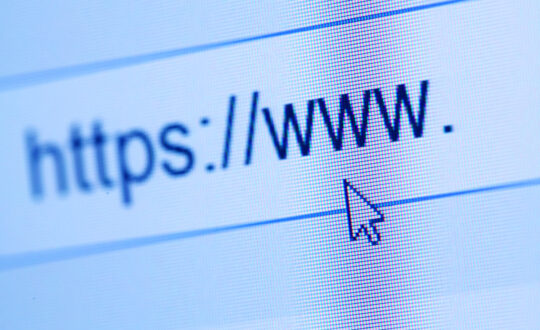自サイトを多くの人に知ってもらいたい場合は、SEO対策を行ないクリック率を高めていきます。
しかしウェブ検索を行なうユーザーには、サイトに入ったもののすぐに帰ってしまう、途中で読むのを中断し別のサイトへ行ってしまうといった人もいます。
最後までサイトを閲覧してもらうためには、直帰率や離脱率といった言葉にも注目しながら対策を行なうことが重要です。
今回は、直帰率と離脱率について、それぞれの違いや確率が上がる場合の原因と改善方法などを解説します。
直帰率とSEOとの関係性についても触れていくので、自サイトを運営している人はぜひご覧ください。
Contents
直帰率について

直帰率と離脱率について考えるとき、まずは直帰率という言葉の意味から見てみましょう。
直帰率とは、ユーザーがサイトに訪れ、その後サイト内の別ページに行くことなく、最初に閲覧したページを最後に直帰してしまう割合を指します。
1つのサイトにおいて、1ページのみを閲覧された場合ということになります。
この直帰率は、ある計算方法で詳しい数字を出すことが可能です。
~直帰率の計算方法~
ページの直帰数÷そのページから始まったセッション数×100
ツールで簡単に計算をすることも可能ですが、自身で計算する場合は上記の式に当てはめることで直帰率を算出できます。
直帰率と離脱率の違いとは?
直帰率について見ているとき、離脱率という言葉を見かけることがあります。
一見違いがわかりにくい直帰率と離脱率、両者にはどのような違いがあるのでしょうか?
ここでは、離脱率の説明から、直帰率と離脱率の違いについてまとめていきます。
離脱率とは
離脱率とは、具体的には以下のような行動を示します。
- ブラウザのもどるボタンを押し、サイトの外に出てしまう
- サイト内に貼られているリンクをクリックし、別サイトへ飛ぶ
- 閲覧しているページを最後にブラウザを閉じる
- 30分間特に何もせず、サイトを放置する
- セッションすることなく午前0時を回る
上記のような状態を離脱といい、離脱率も直帰率と同じように計算式を用いて詳しい割合を出すことが可能です。
~離脱率の計算方法~
そのページの離脱数÷そのページのセッション数×100
直帰率と似た計算式で出すことができます。
直帰率と離脱率の違い
直帰率と離脱率について見てきたなかで、違いが曖昧でわかりにくいと感じる人も多いはずです。
そこで、両者の違いについて詳しく見てみましょう。
直帰率は、前述した通り、ユーザーがサイトに訪れ、その後サイト内の別ページに行くことなく、最初に閲覧したページを最後に直帰してしまう割合です。
次に離脱率とは、特定のページがセッションの最後となった割合を指します。
ここから、「離脱」の中に直帰が含まれることもわかります。
サイト内のページを1ページのみ閲覧してから離脱した場合は、直帰に当たります。
直帰率を確認するための方法

自サイトの直帰率は、ツールを使って調べることができます。
ここでは、直帰率を調べられるツールをご紹介します。
Googleアナリティクス
無料かつ簡単に利用できるのが、Googleアナリティクスです。
Googleアナリティクスでは、直帰率を調べる方法が3通りあります。
何の直帰率を調べるかで確認の方法が異なってくるため、以下を参考にしてください。
1 サイト全体の直帰率を確認する方法
オーディエンスのなかの概要をクリックし、ユーザーサマリーを表示。
セッションとなっている指標のところを直帰率に変更する。
右上にあるセレクトボックスを活用すると、知りたいデータの期間を選択することもできる。
2 各参照元の直帰率を確認する方法
集客からすべてのトラフィックを選択し、参照元、メディアの順にクリックしていく。
3 各ページの直帰率を確認する方法
行動からサイトコンテンツに入り、すべてのページをクリックすることで確認が可能。
ツールを活用すると競合サイトの直帰率も調べることができる
直帰率を確認すると、自サイトと他のサイトを比較する際には役立てることができます。
業界やサイトの特徴などによって異なるのが直帰率でもあるため、自サイトと類似したサイトを参考にすることが重要となるのです。
競合サイトの直帰率を調べるときは、Googleアナリティクスとは異なる別のツールを使って行なう方法があります。
ここでは、競合サイトの直帰率を調べられるツールをご紹介します。
SimilarWeb
データが見やすく初心者にもおすすめとされているツールが、こちらのSimilarWebです。
アクセス数や直帰率などを調べられる他、競合サイトの存在とその詳細を確認できるのが特徴となっています。
競合サイトに訪問、ワンクリックで簡単に分析結果を表示という方法で、直帰率を知ることが可能です。
有料版もあるものの、簡単な機能のみで良い場合は無料版で十分でしょう。
直帰率の目安とは

自サイトの直帰率を確認した際、数字が低ければ良いのか、また高い場合はどのような対策を取れば良いのかなどと対応に悩むこともあるでしょう。
直帰率はページの特性によって異なるため、数字が高くても良い場合があるのです。
たとえば地図のページであれば、目的地にたどり着くことができると良いわけなので、そこでページを見終えるのは当然です。
ページの内容に合わせて直帰率を検討していくことが重要なのです。
ここから直帰率の目安は、サイトのジャンルやページの種類などにより大きく異なることがいえます。
直帰率はSEOに影響するのか?
直帰率は、SEOに直接影響を及ぼすわけではありません。
直帰率が高いと検索順位が低くなる、その反対に直帰率が低いと検索順位は上位になるということではないため、それほど心配する必要はないでしょう。
一方、直帰率の数字を見ることで、自サイトがユーザーから求められている内容を提供で来ているかを確認することができます。
直帰率が低いことで、ユーザーが見たくなるようなページを用意できているという目安にもなるのです。
直帰率の数字はSEOに直接影響はないものの、自サイトの問題点や将来性などを検討していく際には一つの指標となります。
直帰率が高くなる原因
直帰率は、高くなる原因がいくつか考えられます。
ツールで見てみたときに直帰率が高かった、原因は何なのかと、次の対策を取る際に知っておく必要があります。
ここでは、直帰率が高くなる原因について解説します。
サイトにページが1ページしかない
サイトにページが1ページしかない場合、そのページを閲覧したユーザーは自然と直帰します。
他のページがなく、それ以上サイトにいても仕方がないと判断されるためです。
サイトの直帰率を意識するときは、ページ数も重要となるのです。
ユーザーの目的とサイトの内容が異なる
ユーザーは、自身が知りたい情報についてキーワードを入力し検索します。
数多くのウェブコンテンツがあるなか、良かれと思ってクリックしたサイトに期待していた情報が掲載されていない場合もあります。
思っていた内容と違う、知りたいことが載っていないサイトと認識された時点で、直帰率も高くなるのです。
ページの表示速度が遅い
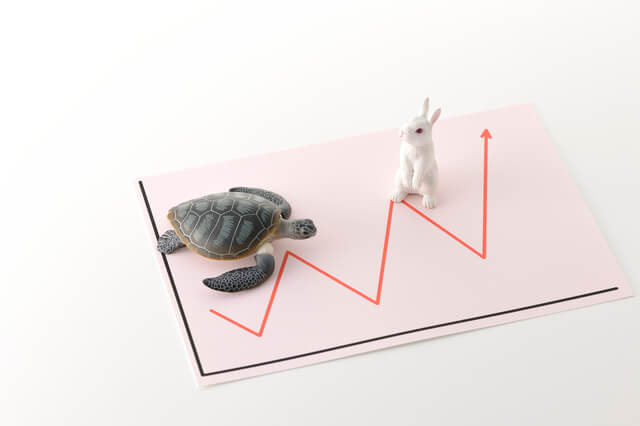
検索結果から気になるコンテンツをチェックするためには、クリックをして次のページに進みます。
このとき、サイトのページがいつまで経っても表示されない、もしくはすべて表示されるまでに時間がかかるとき、直帰率も高まってしまいます。
調べているユーザーがストレスを感じ、サイトの内容が表示される前に別のサイトをクリックしてしまう可能性が高いです。
ページの表示速度によって直帰率が変わってくるという点も覚えておきましょう。
サイトデザインが見づらく、ページが読みづらい
訪れたサイトが全体的に見づらく、どこにどのような情報が載っているかわからないという場合も直帰率が高くなる原因です。
知りたい情報がすぐに得られず、ユーザーはいら立ちを感じてしまう恐れがあります。
早々に戻るボタンを押し、別サイトを閲覧する可能性も高いです。
サイトのデザインやカラーも、ユーザーには大きな印象を与えます。
見やすいサイトであるかを意識しながらコンテンツを作り上げることは、直帰率を改善する際にも有効です。
直帰率が高くなる原因を追究する際、自サイトのデザインやページの見やすさにも注意してみましょう。
内部リンクが設置されていない
コンテンツ内には、内部リンクを設置することでよりSEOに特化したサイトになるといいます。
この内部リンクが設置されていない場合、ユーザーの遷移先がなくなるため、自然と直帰率も高くなってしまいます。
一方、内部リンクが設置されていると、他の記事やページに飛ぶことが可能なので、サイトの潜在時間も長くなるでしょう。
直帰率が高い原因を考えるとき、内部リンクの有無も確認してみると良いです。
スマートフォンで見たときにサイトが見づらい
直帰率を意識するとき、スマートフォンでも見やすいサイトであるかも重視したいです。
最近ではパソコンやタブレットだけでなく、スマートフォンもパソコンのように利用する人が増えています。
スマートフォンは常に手元に置いていることが多く、思い立ったら気軽にインターネット検索ができるという利点から活用する人が多いです。
ここから、スマートフォンでも見やすいサイトづくりを心がけることが大切なのです。
スマートフォンの画面で見づらいとなると、ユーザーは別のサイトをクリックしたくなるでしょう。
スマートフォンで見やすいかどうかは、直帰率だけでなくSEOにも大きく影響してきます。
検索順位にも関係してくるため、直帰率を改善する場合はスマートフォンでの見やすさにも注目してみてください。
直帰率を改善する方法
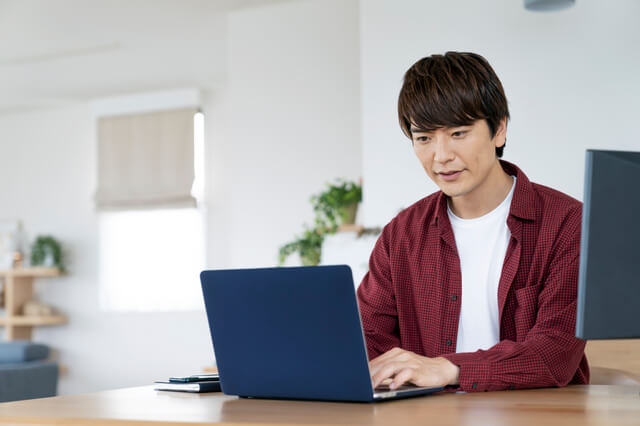
直帰率が高くなる原因を理解したところで、最後に直帰率を改善する方法について詳しく解説します。
自サイトの直帰率の高さに関する原因が判明したら、さっそく改善方法を実践してみましょう。
ページの表示速度を改善する
ページの表示速度が遅いと、ユーザーはイライラして別のサイトへ移ってしまう可能性が高いです。
せっかく有益な情報を提供できているサイトであっても、ページの読み込みが遅いとユーザーは離れていってしまいます。
そこで、自サイトのページがどれくらいの速さで表示されるかを確認してみましょう。
表示速度が遅くなればなるほど、直帰率も高くなるのが現状です。
画像の圧縮などの対策を行ない、ページの表示速度を改善することが重要です。
【合わせて読みたい記事】
コンテンツ内に画像や動画を挿入する
直帰率を改善するためには、コンテンツ内の見やすさ、わかりやすさに注目することも大事です。
小さな文字で文章ばかり載っているサイトよりも、適宜画像やリストが挿入されていたり、わかりやすく解説された動画が紹介されているサイトの方が見やすいです。
文章ばかりのコンテンツでは、ユーザーも疲れてしまいます。
そこで、自サイトのコンテンツを見直し、画像や動画などを挿入してみましょう。
内容に合った画質の良い画像や動画を挿入する対策を取り、直帰率の改善を図ってみてください。
【合わせて読みたい記事】
記事内で改行や箇条書きを活用する
情報を求めてユーザーがサイトを閲覧する際、サイトの見やすさと読みやすさも関係していると述べました。
ここから、より読みやすいコンテンツを作成するため、記事内に改行や箇条書きを活用することも意識してみてください。
改行されていることで文章が読みやすくなり、箇条書きによって情報が入ってきやすいというメリットがあります。
読みやすい記事であれば先に進むことができるため、直帰率の改善にもつながるのです。
ファーストビューの内容を充実させ、スマートフォンでも見やすいサイトを
ファーストビューとは、ユーザーがサイトに訪れたとき最初に見る範囲のページを指します。
スクロールせずに目に入ってくる情報であり、この部分にサイトの内容や重要な情報が記載されていると、さらに先へ読み進めてもらうことが可能です。
このサイトには求めている情報が載っていると判断してもらえることで、直帰率の改善につながります。
同時に、スマートフォンでも見やすいサイトづくりを心がけたいです。
スマートフォンでページを読み込んだ際にも、大事な情報が一目でわかるようまとめておく必要があります。
パソコン用だけでなくスマートフォンにも対応できるようサイトを整え、多くのユーザーに閲覧してもらえるようにしましょう。
スマートフォンでの見やすさはSEO対策においても重視すべき点とされているため、対応しておくと安心です。
【合わせて読みたい記事】
ユーザーの検索意図を満たすページづくりを意識する

スピーディーに表示され、一目でサイトの情報がわかるページづくりを心がけることが重要と紹介しましたが、このとき忘れてはならないのがユーザーの検索意図を満たすページになっているかという点です。
サイトに訪れたユーザーにとって有益な情報が載っていない場合、自然と別のサイトを参考にするはずです。
記事を最後まで読み進めることなく、途中で直帰してしまう可能性があります。
たとえば、子どものスニーカーを探しているのに大人用のスニーカーしか紹介されていないサイトは、ユーザーにとって参考になりません。
求めている情報がないと判断され、別のサイトへ移ってしまいます。
一方、大人用スニーカーを、ジャンル別やサイズ別、性別ごとに紹介しているようなサイトは、ユーザーもじっくりと閲覧することができるはずです。
SEOにおいても重要とされる検索キーワードを意識し、そのキーワードを軸としたページづくりを行なうことが大切なのです。
【合わせて読みたい記事】
アンカーリンクで目次の設置
サイトに訪れたものの、知りたい情報がどこに記載されているかわからないという状態のとき、ユーザーは離れていってしまいます。
そこで、アンカーリンクを使って目次の設置を行ないましょう。
目次を見た時点で、どこに何が書かれているかわかるため、ユーザーは知りたい情報のもとへ飛ぶことができます。
できる限り早く情報を提供することで、直帰率の改善につながるのです。
記事を作成し、見出しなどの調整を行なうとき、目次の設置も忘れないようにしましょう。
直帰率を意識し、SEOに強く、多くのユーザーが訪れるようなサイトを目指そう
最初に表示されたサイトのページを最後にユーザーが離れてしまう直帰率を改善するためには、その原因を知ることが大切です。
原因を知ることで、自サイトにおいてどのような対策が必要かが見えてきます。
そのうえで、直帰率を改善するための方法を参考に対策を取ってみましょう。
直帰率を改善していくことで、多くのユーザーが訪れるようなSEOに強いサイトへと成長していくことも可能です。
細かい部分に注目し、ユーザー目線でサイトづくりを行なうことが重要なポイントとなるのです。