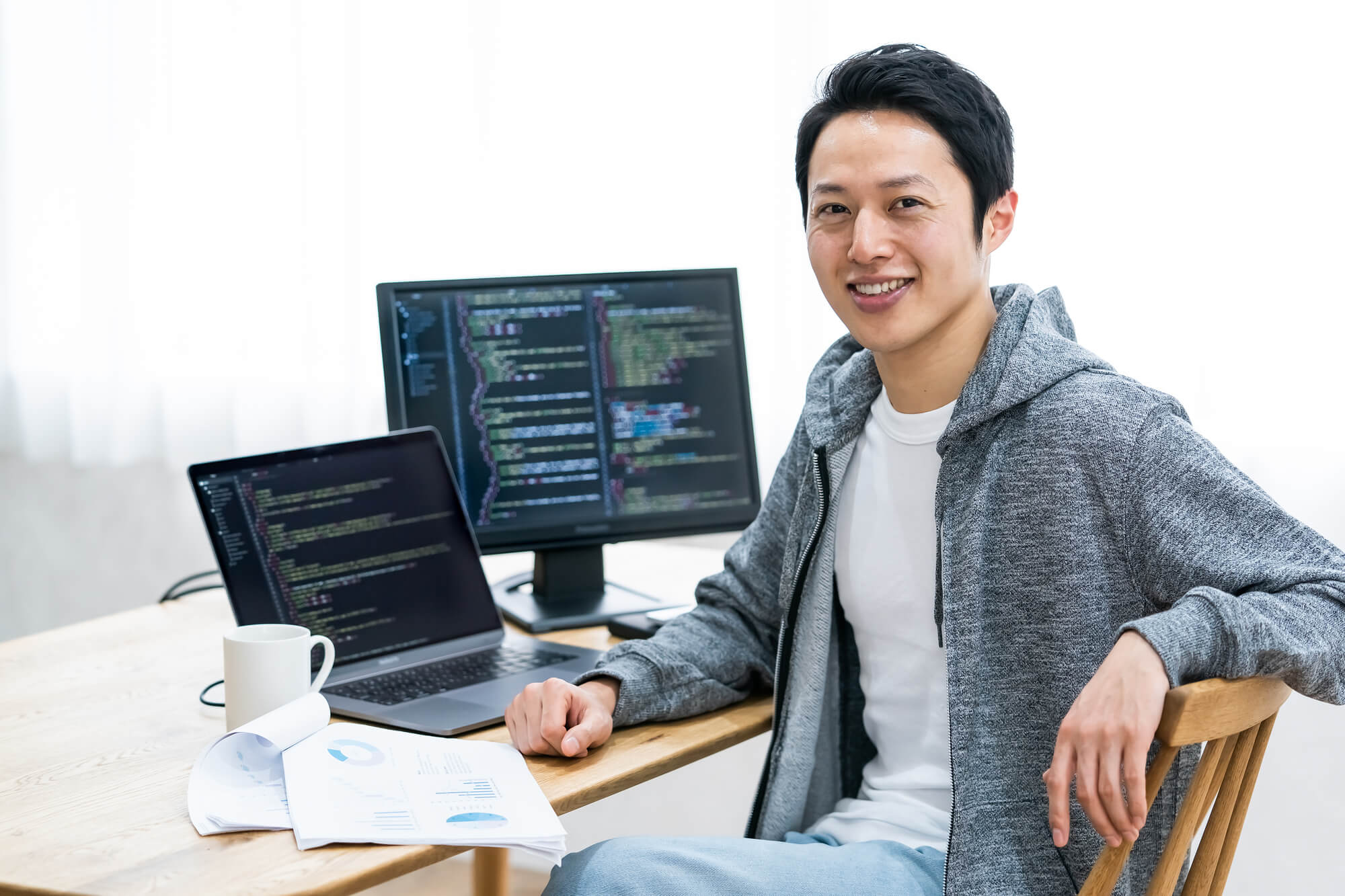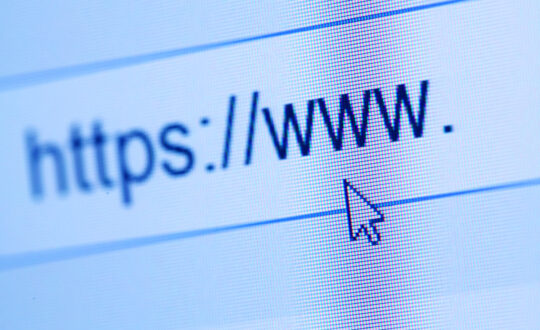「構造化データって何?SEOに関係があるの?」
「構造化データの設定方法や取り入れ方について知りたい」
自サイトを運営する人が増えた今、マーケティング業界では集客に関する様々な施策が行なわれるようになりました。
特にSEO対策に取り組むサイト運営者が増えており、ウェブ上からの集客を期待する会社も多いです。
ユーザーの目に留まる存在となるためには、ユーザーがウェブ検索をした際にどのように表示されるかが重要なポイントとなります。
そこで注目されているのが、構造化データです。
今回は、構造化データとは何なのか、SEOとの関係性やメリット、具体的な設定方法などについて詳しく解説します。
構造化データについての知識を得て、自サイトを多くのユーザーに認知してもらえるようにしましょう。
Contents
構造化データとは

構造化データとは、HTMLで書かれた情報を検索エンジンが理解しやすいようにするためのデータです。
これまで、検索エンジンはHTMLで記載されたものを単なる記号として認識することしかできませんでした。
記号のままの状態では、内容を理解すことが難しかったのです。
そこで検索エンジンにHTMLの内容を認識してもらえるよう、文字の意味や背景などを理解させようとしたものが構造化データです。
ただの文字列ではなく意味を理解させようとする考え方をセマンティックWEBともいい、ウェブの利便性を高めることを目的にデータを検索エンジンが理解できるように意味づけしました。
構造化データをHTMLのタグを使って実装することをマークアップと言います。
構造化データの利用は、世界中の人が快適にサイトを閲覧できるようにするというGoogleの考え方とも一致します。
構造化マークアップとSEOの関係性

構造化マークアップは、直接的にSEO効果が期待できるものではないと言われているものの、構造化マークアップすることで検索エンジンに認識されやすくなるのは事実です。
リッチリザルトが表示されるとユーザー体験が向上し、サイトに訪れる人も増えるでしょう。
このように、構造化マークアップによって、間接的なSEO効果が期待できるのです。
すぐにSEO効果が現れるものではありませんが、長い目で見て構造化マークアップを実践していくと検索順位を高めることにつながります。
【合わせて読みたい記事】
構造化データのメリット
構造化データの特徴についてご紹介していますが、メリットとデメリットについても確認した上で構造化データの利用を検討してみましょう。
構造化データのメリットには、以下のような点が挙げられます。
検索エンジンがサイトの内容を認識しやすくなる
構造化データを活用すると、検索エンジンがサイトの内容を理解しやすくなります。
属性や属性値などを用いて構造化データを設定しておくと、サイトの内容をGoogleのクローラーが速やかに把握できるようになるのです。
サイトの内容だけでなく、会社名や所在地なども構造化データによって検索エンジンに伝えることができます。
検索エンジンに自サイトの内容を正しく理解してもらえるというのが、構造化データのメリットといえるのです。
SEO対策としても、構造化データは大きく影響してくるといえます。
検索結果一覧にリッチスニペットが表示される場合がある
構造化データの設定をしておくと、検索結果のところにリッチスニペットが表示されることがあります。
たとえば飲食店を経営している人がサイトを作っている場合、ユーザーがエリアやランチ、カフェなどのキーワードで調べた際に詳しい情報が検索結果の画面に表示されるようになっているのがリッチスニペットです。
競合サイトとの差別化ができたり、ユーザーにクリックされやすくなるというのがリッチスニペットの特徴なので、SEO対策にも有効です。
構造化データの設定によりリッチスニペットが表示されることで、ユーザーが気になる情報を一覧で紹介できるため、飲食店や販売店においては集客にもつながります。
見出しや本文以外の情報でも検索結果表示が狙える
構造化データは見出しや本文以外にも指定ができるため、適切に活用すれば検索結果に大きく影響する場合があります。
見出しや本文以外の情報とは、具体的に以下のようなものが挙げられます。
- 画像
- 口コミ
- 住所
- 営業時間など
見出しや本文以外の要素も表示できることで、ユーザーの関心を引きやすくなります。
その結果、クリック率向上も期待できるようになるのです。
E-E-A-Tにも効果が期待できる
Googleは「検索品質評価ガイドライン」を定期的に更新していますが、2022年12月に更新した際にこれまでの評価基準としてあったE-A-TをE-E-A-Tとすることを発表しました。
Eがもう1つ付け加わり、Experience(経験)が追加されたのです。
コンテンツの信頼性を高めるためには経験も重要であり、経験者によるコンテンツを高く評価するようになりました。
このことから、構造化データの中に著者の情報も入れておくことでE-E-A-Tを高めることができ、Googleから高く評価されるサイトとなれるのです。
構造化データのデメリット

メリットを見るとぜひ設定しておきたいと感じる構造化データですが、設定に取り掛かる前にデメリットがある点についても確認しておきましょう。
構造化データのデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
専門知識が必要となる
構造化データのデメリットは、専門知識が必要になることです。
構造化データには様々な形式があり、形式によって記述方法が異なります。
さらに複数の属性や属性値があり、定期的に新しいものが増えていきます。
そのため、構造化データの種類や記述方法について理解を深めた上で、定期的に増えていく属性なども覚えていく必要があるのです。
素人がやみくもに行えばかえってサイトの表示が重くなり、サイトの読み込み速度が落ちるなどのSEOへの影響が懸念されます。
ここから、構造化データを適切に設定するためには専門知識が必要になるといえるのです。
クリック数増加が確実なわけではない
構造化データを利用することによって、クリック数増加が確実になるわけではない点もデメリットといえます。
リッチリザルトの表示形式によっては、ユーザーにクリックしてもらえずに終わってしまうこともあるのです。
リンクをクリックするまでに知りたい情報が得られた場合、サイトに訪れることは少ないでしょう。
そのため、構造化データを設定する際は、ユーザーはクリックしたくなるような情報を入れることが重要になります。
クリック数増加が確実ではないと把握し、慎重に設定しましょう。
実装までに時間がかかる場合がある
構造化データのデメリットには、実装までに時間がかかるケースがあるという点も挙げられます。
設定した構造化データは、内容が正しいか専用ツールで確認しなければなりません。
このときエラーが出ると、その内容をもとに修正をして検証・改善を図っていくことになります。
改善が見られない場合は、繰り返し修正を行ないながらエラーの状況を確認していかなければなりません。
作業に慣れてくるとエラーが出ずに設定が完了できますが、最初のうちはエラーが起きることも多いです。
構造化データを設定していく上で重要な言葉

構造化データを理解して設定していく際、重要となる言葉があります。
重要な言葉は2つあるので、それぞれの意味を理解しておきましょう。
ボキャブラリー
ボキャブラリーとは、構造化データを設定するときに何についての情報なのかを定義したものです。
人の名前であればname、住所であればaddressを記述すると、検索エンジンには人の名前や住所であることがわかってもらえます。
Googleは、「schema.org」という規格のボキャブラリーをサポートしており、タイプとプロパティを指定して設定していきます。
シンタックス
シンタックスという言葉も構造化データを設定していくときに大切です。
シンタックスはマークアップするときの仕様を示しており、たとえばGoogleがサポートしているものには以下の3つがあります。
- Microdata
- RDFaLite
- JSON-LD
この3つの中でGoogleが推奨しているものが、JSON-LDです。
HTMLの記述がしやすく、使いやすいところが特徴となっています。
構造化データの設定方法について
構造化データの特徴やメリット・デメリットを押さえた次に、どのように設定していけば良いのかという方法について詳しく見ていきます。
構造化データの書き方は、以下の3通りがあります。
- 構造化データマークアップ支援ツールを活用する
- HTMLファイルに直接書き込んでいく
- データハイライターを使用する
それぞれの設定方法を確認して、どの書き方で進めていくのが良いか考えてみてください。
構造化データマークアップ支援ツールを活用する
HTMLについてあまり詳しくない初心者であれば、構造化データマークアップ支援ツールを使って設定する方法がおすすめです。
専用のツールを使えば、手順に沿って一つずつ進めていくことで無事に構造化データの設定を完了させることができます。
ここでは、実際にどのように構造化データマークアップ支援ツールを活用していけば良いのか、その方法についてご紹介しましょう。
- ツールを開き、その中の「ウェブサイト」のところから「記事」をクリックしてください。
- そこに構造化データを記述したいページのURLを入力します。自サイトのなかでもFAQページや商品情報に関するページを表示させたいときは、該当するボタンをクリックして進めていくと良いです。
- 入力が完了すると、左側にウェブページが表示され、右側に構造化データの情報が表示されます。タイトルなどをクリックすると色が変わるようになっているので、検索エンジンに認識させたい構造化データを選択しましょう。
- 該当する構造化データを選ぶと、右側に自動的に情報が表示され、構造化データをマークアップする情報を入力した上で「HTMLを作成」をクリックしてみてください。
- クリックした後、右側に「JSON-LD」という形式で構造化データが出力されます。出力された構造化データをダウンロードしてHTMLの<head>タグの中に追加すると、設定が完了したことになります。
自動化ツールなので、HTMLの専門的な知識がない人にとっても設定しやすいです。
初めて構造化データの設定を行なうという人は、構造化データマークアップ支援ツールを使ってみてください。
HTMLファイルに直接書き込んでいく
HTMLについてそれなりに知識がある、これまでサイトで実装してきた経験があるという場合は、HTMLファイルに直接書き込んで構造化データの設定を行なうことができます。
直接HTMLで書いていくやり方の方が、より自由に構造化データを記述できるという利点が挙げられます。
さらに、ツールよりも正確に構造化データを作成できるため、少しずつHTMLの書き方を覚えていくことで活用できるでしょう。
HTMLを使って構造化データのマークアップする際は、どの値をどうやって記述していくかを決めていきます。
HTMLでは、値のことをボキャブラリー、記述方法のことをシンタックスという呼び方をします。
ボキャブラリーのところにはサイトのURLや会社名、住所、問い合わせ先などを記述すると良いです。
データハイライターを使用する
HTMLについて詳しくないし、正確にコードを記述する自信がないという場合は、データハイライターを使って設定することもできます。
データハイライターというツールを使うと、HTMLに不慣れな人であっても比較的スムーズに構造化データの設定を進めることができるのです。
データハイライターは、HTMLに構造化データを記述しなくても検索エンジンにサイトの存在を伝えることができるツールとなっています。
構造化マークアップ支援ツールと同じような流れで利用できるのもポイントです。
データハイライターを使って設定を行なう際は、次の手順で進めてみてください。
- Googleサーチコンソールの「検索の見え方」から「データハイライター」、「ハイライト表示を開始」の順に進んでいく
- 対象となるページのURLを指示通りに入力する
シンプルな手順で構造化データの設定ができるようになっています。
初心者であっても、無事に構造化データの設定ができるでしょう。
ただし、URLに規則性がないときやHTMLが複雑である場合、複数ページをまとめてマークアップできない点には注意してください。
参照:データハイライター
構造化タグの種類一覧
構造化データの設定をしていくにあたって、構造化タグが必要となります。
構造化タグにもいろいろな種類があるので、一部を以下にご紹介します。
| 構造化タグ種類 | 解説 |
|---|---|
| <header> | ヘッダーであることを示したタグ。 サイトのなかでも上部に表示される部分で、サイト名や会社情報などを記載することが多い。 ヘッダータグが設定されていることで、サイトに訪れたユーザーは何について紹介されているサイトなのかをすぐに理解することができる。 |
| <article> | 記事であることを示しており、それぞれのセクションが1つの記事であることを意味している。 |
| <nav> | ナビゲーションのことを指しており、ユーザーが求めている情報にたどり着けるようリンク付きで示したテキスト。 ナビゲーションがあることでユーザーは迷わずに別のページで飛べて、SEOの観点からはサイトの回遊率を高めることにもつながる。 どこに記載するかという表示の場所は決まっていないが、フッターに記載されることが多い。 |
| <section> | 見出しをつけることができる文のまとまりを示している。 企業のホームページであれば、ページの中に記載されている社長のあいさつや企業理念など、ページの中で区切りをつけるために用いられる。 |
| <footer> | ページ下部に表示されるフッターであることを示しており、ヘッダーと反対にあたる部分である。 フッターには、多くの場合基本情報の他、外部サイトへの誘導が書かれていることもある。 |
構造化データの記述例
構造化データでは、様々な記述例があります。
一例をご紹介していくので、参考にしてみてください。
- パンくずリスト
- 求人情報
- FAQ
- レシピ
- 著者
- 監修者
それぞれどのように設定していけば良いのか、構造化データの記述例をご紹介します。
パンくずリスト
パンくずリストとは、ユーザーが閲覧しているページがサイト上のどこに位置しているかを表すものです。
サイトの上部に設置されていることが多くなっています。
パンくずリストの構造化データを記述すると、ページの内容について検索結果一覧の段階で的確にユーザーに伝えることができるのです。
ユーザーだけでなく、クローラーにもサイトの内容を認識してもらいやすくなります。
ページの内容や構成について一目でわかるため、SEO効果も期待できるでしょう。
求人情報
求人情報についても構造化データを設定しておくと、仕事を探しているユーザーに気づいてもらいやすいです。
構造化データを設定した場合、検索結果では会社のロゴや求人内容などが一目でわかるよう掲載されます。
リッチリザルトとして表示されることで、条件に合う会社の情報を一覧で確認できるようになります。
求人情報を構造化データで設定する場合は、募集を終了しているなどの関係からユーザーに不信感を抱かれてしまわないよう、こまめな情報更新を忘れないようにしましょう。
ユーザーからだけでなくGoogleからの評価が下がる恐れもあるため、求人情報については定期的に確認をして、変更があった場合はすぐに対処するようにしてください。
FAQ
ユーザーが疑問を抱いたときに閲覧するのが、サイト内のFAQです。
気になったことを知りたい、問い合わせる前にわかることがあれば確認しておきたいというユーザーがいることから、サイトのなかでもFAQは閲覧される確率が高いです。
閲覧される率が高いFAQにおいて構造化データを設定する場合は、ユーザーが抱えているであろう悩みに応じて設定してみましょう。
検索結果のところで自身が抱えている悩みに対するFAQが表示されると、すぐに内容を確認でき、問題を解決できる可能性があります。
サイトのクリック率向上にもつながるでしょう。
レシピ
料理のレシピにも構造化データを設定すると、ユーザーが調べた細かい検索に関しても検索結果に反映されやすくなります。
構造化データの設定により、検索結果では画像などと一緒に出来上がるまでの時間なども記載されており、ユーザーは気になるレシピをクリックできます。
数多く存在するレシピのなかから、構造化データの設定をしているレシピはユーザーに注目されやすいです。
監修者
構造化データでは、監修者の情報を記述することもできます。
どのような人がサイトの記事を監修しているのかがわかり、その記事を信頼できるかをユーザーは判断できるのです。
監修者には、免許を持っている人や権威を持っている人が多いです。
ユーザーはより安心して記事を読み進めることができます。
構造化データでも監修者の情報を含めておくと、サイトに訪れるユーザーの数も増やしていくことができるでしょう。
信頼性の高い記事であると紹介することで、SEO対策にもつながります。
著者
著者に関する情報も、構造化データで記述することができます。
著者名だけでなく記事のタイトルなども記載できるので、検索結果で表示される確率が高まります。
リッチリザルトに著者の情報が表示されると、名前や画像など様々な情報を一度に知ることができるのが特徴です。
もう少し詳しく著者の情報を知りたい場合は、リンクを辿って情報を入手することができます。
著者の情報を記載するケースにおいても、構造化データを活用するとユーザーの目に留まりやすくなるのです。
構造化データの確認ができるマークアップ支援ツール一覧
状況に応じた方法で構造化データの設定をしてみたら、正しく反映されているかを確認する必要があります。
そのようなときに活躍するのが、構造化データのテストツールです。
HTMLに詳しくなくても使えるツールとなっているので、ぜひご確認ください。
Googleサーチコンソール
GoogleサーチコンソールはGoogleが公式で提供しているツールであり、構造化データの設定エラーやユーザーがサイトに訪れるまでの問題点などを洗い出してくれます。
以下の手順で、構造化データの確認をしてみましょう。
- Googleサーチコンソールに入り、URLプレフィックスを選ぶ
- 調べたいURLを入力する
- 所有権の確認について表示され、Googleアナリティクスなどを使っていない場合はHTMLファイルをアップロードする方法を選択する
- 検索パフォーマンスやURL検査などを調査して、構造化データが適切に機能しているかを調べる
スキーマ マークアップ検証ツール
構造化データのテストをする際、スキーマ マークアップ検証ツールというものもあります。
構造化データのマークアップ状況を無料で調べられるツールで、schema.orgで設定されているすべての構造化データを簡単に検証できるようになっています。
ツールの使い方は、以下の通りです。
- 構造化データテストツールから、スキーマ マークアップ検証ツールを選ぶ
- 該当するページのURLまたはコードを選び、「テストを実行」をクリックする
スキーマ マークアップ検証ツールではGoogleが定めているリッチリザルトの表示に必要なものが抜けているときは、その内容を確認することができません。
Googleが公式で提供しているリッチリザルトテストも併用して、構造化データの状況をより詳しく調べておくのがおすすめです。
リッチリザルトテスト
リッチリザルトテストでは、構造化データによって表示されるリッチリザルトの確認ができます。
- 該当するページのURLもしくはコードを入力する
- 「URLをテスト」または「コードをテスト」をクリックする
- 正しくマークアップされていれば、「〇件の有効なアイテムを検出しました」と表示される
構造化データは正しく理解して設定していこう!ツールを活用するのもおすすめ
構造化データは、サイトの存在をユーザーにアピールするためにはぜひ取り入れたいものです。
サイトの注目度を高められる点から、SEO対策においても嬉しい効果が期待できます。
構造化データの仕組みや特徴を押さえて、始めやすい方法で設定をしてみましょう。
専用ツールをいくつか確認しておくと、効率よく構造化データの設定ができます。
構造化データを取り入れて、一人でも多くのユーザーに自サイトを知ってもらいましょう。